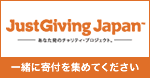2011年11月08日
「遺体―震災、津波の果てに 」
震災以降 支援の活動を続けてきましたが、ある方から薦められた本です。
震災に関して多くの書籍や写真集など発売されていますが、この本は全く別の視点で書かれた本です。
「遺体―震災、津波の果てに 」 著者:石井 光太
ヘビーな内容を書いていますので以降は読みたい方だけ読んで下さい。 続きを読む
震災に関して多くの書籍や写真集など発売されていますが、この本は全く別の視点で書かれた本です。
「遺体―震災、津波の果てに 」 著者:石井 光太
ヘビーな内容を書いていますので以降は読みたい方だけ読んで下さい。 続きを読む
タグ :東日本大震災
2011年03月06日
「夜と霧」そしてコーチング
さて今日、紹介する本は古くから読み継がれている作品である「夜と霧」という本です。
みなさんはこの本 読んだことはありますか?
心理学者であるカール・ロジャースなどからちょっと辿っていたらこの作品に出会いました。
この本の中では、強制収容所で体験した出来事など綴った前半と、そこから導きだされる心理学者としての人の心の考察が後半に書かれています。
【本より引用】
・精神の自由
被収容者は、行動的な生からも安逸な生からもとっくに締め出されていた。しかし行動的に生きることや安逸に生きることだけに意味があるのではない。そうではない。およそ生きることそのものに意味があるとすれば、苦しむこと にも意味があるはずだ。苦しむこともまた生きることの一部なら、運命も死ぬことの生きることの一部なのだろう。苦悩と、そして死があってこそ、人間という存在ははじめて完全なものになるのだ。
「苦しみ」や「死」があるからこそ、人間として それも 精神が自由な人間として生きている証である・・そんな風に思える一節です。
・「運命-賜物」
ひとりの人間が避けられない運命と、それが引き起こすあらゆる苦しみを甘受する流儀には、きわめてきびしい状況でも、 また人生最後の瞬間においても、生を意味深いものにする可能性が豊かに開かれている。(中略)あの収容所の心理を地でいく群れの一匹になりはてたか、苦渋にみちた状況ときびしい運命がもたらした、おのれの真価を発揮する機会を生かしたか、あるいは生かさなかったか。そして「苦悩に値」したか、しなかったか。
このような問いかけを、人生の実相からほど遠いとか、浮世離れしているとか考えないでほしい。(中略)人間の内面は外的な運命より強靱なのだということを証明してあまりある。
それはなにも強制収容所にかぎらない。人間はどこにいても運命と対峙させられ、ただもう苦しいという状況から精神的になにかをなしとげるかどうか、という決断に迫られるのだ。
強制収容所という(特殊な)環境だけでなく、いつでも、どこでもそんな選択や決断を常にしている・・・。何気ない決断や選択によって大きくその後の人生が変わった。。そんなことって多々ありますよね。。。
・目的を見失った人
人は未来を見すえてはじめて、いうなれば永遠の相の元ににのみ存在しうる。これは人間ならではのことだ。したがって存在が困難を極める現在にあって、人は何度となく未来を見すえることに逃げ込んだ。(中略)しかし未来を、自分の未来をもはや信じることができなかった者は、収容所で破綻した。そういう人は未来とともに精神的なよりどころを失い、精神的に自分を見捨て、身体的にも精神的にも破綻していったのだ。
コーチングでは未来がどうありたいか?という目で見ていきます。
自分の未来が見えない そんな時 人は誰かに助けを求めて、誰かに話を聞いて欲しい そう感じると自分の経験からも分かります。
薔薇色の未来・・・そこまでは求める必要はないと思いますが、日常の、ほんとうに小さな出来事や幸せを感じる出来事が人の命を繋げていくのだろうと思います。
ニーチェの言葉
「なぜ生きるかを知っている者は、どのように生きることにも耐える」
そして何より惹かれたのはこの文章でした。
・生きる意味を問う
わたしたちが生きることからなにを期待するのではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ、ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。哲学用語を使えば、コペルニクス的転回が必要なのであり、もういいかげん、生きることの意味を問うのはやめ、わたしたち自身が問いの前に立っていることを思い知るべきなのだ。生きることは日々、そして時々刻々、問いかけてくる。わたしたちはその問いに答えを迫られている。考えこんだり、言辞を弄することによってではなく、ひとえに行動によって、適切な態度によって、正しい答えは出される。
・自分がどんな風に生きればよいか?そんな問いをしてその答えに従って行動すること。
・行動することでしか、人生は変わらない
上記2つは正にコーチングの考え方です。
だれもその人から苦しみを取り除くことはできない。だれもその人の身代わりになって苦しみをとことん苦しむことはできない。この運命を引き当てたその人自身がこの苦しみを引きうけることに、ふたつとないなにかをなしとげるたった一度の可能性はあるのだ。
答えはクライアントの中にある・・・そうコーチングでは学びます。
コーチは寄り添い励ましたり、提案をしたりすることは出来ますが、そのクライアントの人生全てを背負いそのクライアントの代わりに生きていくことは出来ません。
その苦しみはその人が大きく成長するために訪れた「機会」なのだと受け止め、そこからでしか得ることが出来ないものを感じ、その人が「したい」と思っていることを成し遂げるためのエネルギーに変えていく。。それが未来を大きく変えていく方法・・・・そんな風に読み解くことが出来ました。
この本に書かれた内容は自分に向かって多くの「問い」を投げかけてくれた本でした。
この本の作者 V・E・フランクル ・・・彼が書いた他の本ももっと読んでみたい・・そう感じました。
みなさんはこの本 読んだことはありますか?
心理学者であるカール・ロジャースなどからちょっと辿っていたらこの作品に出会いました。
この本の中では、強制収容所で体験した出来事など綴った前半と、そこから導きだされる心理学者としての人の心の考察が後半に書かれています。
【本より引用】
・精神の自由
被収容者は、行動的な生からも安逸な生からもとっくに締め出されていた。しかし行動的に生きることや安逸に生きることだけに意味があるのではない。そうではない。およそ生きることそのものに意味があるとすれば、苦しむこと にも意味があるはずだ。苦しむこともまた生きることの一部なら、運命も死ぬことの生きることの一部なのだろう。苦悩と、そして死があってこそ、人間という存在ははじめて完全なものになるのだ。
「苦しみ」や「死」があるからこそ、人間として それも 精神が自由な人間として生きている証である・・そんな風に思える一節です。
・「運命-賜物」
ひとりの人間が避けられない運命と、それが引き起こすあらゆる苦しみを甘受する流儀には、きわめてきびしい状況でも、 また人生最後の瞬間においても、生を意味深いものにする可能性が豊かに開かれている。(中略)あの収容所の心理を地でいく群れの一匹になりはてたか、苦渋にみちた状況ときびしい運命がもたらした、おのれの真価を発揮する機会を生かしたか、あるいは生かさなかったか。そして「苦悩に値」したか、しなかったか。
このような問いかけを、人生の実相からほど遠いとか、浮世離れしているとか考えないでほしい。(中略)人間の内面は外的な運命より強靱なのだということを証明してあまりある。
それはなにも強制収容所にかぎらない。人間はどこにいても運命と対峙させられ、ただもう苦しいという状況から精神的になにかをなしとげるかどうか、という決断に迫られるのだ。
強制収容所という(特殊な)環境だけでなく、いつでも、どこでもそんな選択や決断を常にしている・・・。何気ない決断や選択によって大きくその後の人生が変わった。。そんなことって多々ありますよね。。。
・目的を見失った人
人は未来を見すえてはじめて、いうなれば永遠の相の元ににのみ存在しうる。これは人間ならではのことだ。したがって存在が困難を極める現在にあって、人は何度となく未来を見すえることに逃げ込んだ。(中略)しかし未来を、自分の未来をもはや信じることができなかった者は、収容所で破綻した。そういう人は未来とともに精神的なよりどころを失い、精神的に自分を見捨て、身体的にも精神的にも破綻していったのだ。
コーチングでは未来がどうありたいか?という目で見ていきます。
自分の未来が見えない そんな時 人は誰かに助けを求めて、誰かに話を聞いて欲しい そう感じると自分の経験からも分かります。
薔薇色の未来・・・そこまでは求める必要はないと思いますが、日常の、ほんとうに小さな出来事や幸せを感じる出来事が人の命を繋げていくのだろうと思います。
ニーチェの言葉
「なぜ生きるかを知っている者は、どのように生きることにも耐える」
そして何より惹かれたのはこの文章でした。
・生きる意味を問う
わたしたちが生きることからなにを期待するのではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ、ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。哲学用語を使えば、コペルニクス的転回が必要なのであり、もういいかげん、生きることの意味を問うのはやめ、わたしたち自身が問いの前に立っていることを思い知るべきなのだ。生きることは日々、そして時々刻々、問いかけてくる。わたしたちはその問いに答えを迫られている。考えこんだり、言辞を弄することによってではなく、ひとえに行動によって、適切な態度によって、正しい答えは出される。
・自分がどんな風に生きればよいか?そんな問いをしてその答えに従って行動すること。
・行動することでしか、人生は変わらない
上記2つは正にコーチングの考え方です。
だれもその人から苦しみを取り除くことはできない。だれもその人の身代わりになって苦しみをとことん苦しむことはできない。この運命を引き当てたその人自身がこの苦しみを引きうけることに、ふたつとないなにかをなしとげるたった一度の可能性はあるのだ。
答えはクライアントの中にある・・・そうコーチングでは学びます。
コーチは寄り添い励ましたり、提案をしたりすることは出来ますが、そのクライアントの人生全てを背負いそのクライアントの代わりに生きていくことは出来ません。
その苦しみはその人が大きく成長するために訪れた「機会」なのだと受け止め、そこからでしか得ることが出来ないものを感じ、その人が「したい」と思っていることを成し遂げるためのエネルギーに変えていく。。それが未来を大きく変えていく方法・・・・そんな風に読み解くことが出来ました。
この本に書かれた内容は自分に向かって多くの「問い」を投げかけてくれた本でした。
この本の作者 V・E・フランクル ・・・彼が書いた他の本ももっと読んでみたい・・そう感じました。
2010年10月30日
こんな図書館どうですか?
少し前 東京の読書会に参加するため、新幹線で向かったのですが、その時に買った『DIME』にこんな記事が書かれていました。
**************************************
ある企画会社に製造メーカに勤めていたOLの方が訪れてこんな依頼をされたそうです。
『人と人がつながることのできる温かい場所を作りたい』・・・・
でもその願いは 彼女の会社から ではなく 彼女自身から の依頼だったそうです。それもOL生活で貯めたお金の300万を切り崩して『人の集う空間を企画してほしい』そんな依頼をしました。
そんなリクエストを受けたこの企画会社の面々は、その彼女のその心意気に賛同して、損得抜きで応援を始めたそうです。
そしてそんな一人のOLの願いは今夏 世界で一番小さい図書館『人生図書館』として実現したそうです。
そこはまだわずか10畳で、蔵書は80冊しかない図書館だそうです。
でも、その図書館にある一冊一冊には寄贈していただいた有名無名の方々の本への『想い』がたくさんたくさん詰まった、世界でたった一冊しかない本を収蔵している図書館であり、寄贈された本は
・79歳の女性社長は林芙美子さんの『放浪記』
・小学校1年生の女の子は『いいから いいから』という絵本
などがあり、その絵本を推薦した少女のコメントは『このほんをよんで、おともだちにやさしくできるようになったよ』だったそうです。
そして記事はこんな素敵な言葉が書かれていました。
『ここに来れば、誰かの人生の一冊を、無料で自由に読める。人と人が本でつながることができるまさに温かい集いの場なのだ』
*************************************
本には著者の想いが綴られ、そしてその想いを読者が受け取るキャッチボール・・・そしてこの夏 一人の女性の想いから作られた図書館に訪れた人に『著者+読者』の想いが伝わっていく。。。。まるでペイフォワードのような話でとても素敵な話だな~と感じました。
そんな想いを感じた日からしばらくして、今度は朝日新聞に読書週間についての記事があり、作家の瀬戸内寂聴さんのインタビューが書かれていました。(以下 朝日新聞 2010年10月27日付からの引用です。)
**************************************
『よく聞かれますけど、運命の一冊なんて、ないですよ。本に助けられたこともない。ただ、たくさんの本を読んでいるから、自分の身に降りかかったことが特別なこととは思いません。世の中にいくつもあることです。良いことも悪いことも、「全てあり得る」-本を読んだ人は、その当たり前のことが、わかるんじゃないでしょうか』
**************************************
文頭の内容と相反するように感じる方もいるかもしれませんが、俺は瀬戸内さんの考えもありだな・・・そう感じてます。
読んだ本のこの部分に共感した とか この章に心惹かれた・・・など本の一部の「いいとこ取り」もありだと思うのです。。。
さてさて、そんな読むだけで自分の内側でいろいろな事を思い描けるような経験が出来る読書ですが、本への想いや感想をアウトプットすることで、更に自分の中にに落とし込めることが出来る『読書会』を12月に長野市で開催します!!
日時、場所、課題本など詳細はこちらです。フォームからの申込か、このblogの『オーナーへメール』から申し込んでいただいてもオーケーです(*^_^*)
本を読んだ想いを話し聞くことで一冊の本の見方を深めてみませんか?

**************************************
ある企画会社に製造メーカに勤めていたOLの方が訪れてこんな依頼をされたそうです。
『人と人がつながることのできる温かい場所を作りたい』・・・・
でもその願いは 彼女の会社から ではなく 彼女自身から の依頼だったそうです。それもOL生活で貯めたお金の300万を切り崩して『人の集う空間を企画してほしい』そんな依頼をしました。
そんなリクエストを受けたこの企画会社の面々は、その彼女のその心意気に賛同して、損得抜きで応援を始めたそうです。
そしてそんな一人のOLの願いは今夏 世界で一番小さい図書館『人生図書館』として実現したそうです。
そこはまだわずか10畳で、蔵書は80冊しかない図書館だそうです。
でも、その図書館にある一冊一冊には寄贈していただいた有名無名の方々の本への『想い』がたくさんたくさん詰まった、世界でたった一冊しかない本を収蔵している図書館であり、寄贈された本は
・79歳の女性社長は林芙美子さんの『放浪記』
・小学校1年生の女の子は『いいから いいから』という絵本
などがあり、その絵本を推薦した少女のコメントは『このほんをよんで、おともだちにやさしくできるようになったよ』だったそうです。
そして記事はこんな素敵な言葉が書かれていました。
『ここに来れば、誰かの人生の一冊を、無料で自由に読める。人と人が本でつながることができるまさに温かい集いの場なのだ』
*************************************
本には著者の想いが綴られ、そしてその想いを読者が受け取るキャッチボール・・・そしてこの夏 一人の女性の想いから作られた図書館に訪れた人に『著者+読者』の想いが伝わっていく。。。。まるでペイフォワードのような話でとても素敵な話だな~と感じました。
そんな想いを感じた日からしばらくして、今度は朝日新聞に読書週間についての記事があり、作家の瀬戸内寂聴さんのインタビューが書かれていました。(以下 朝日新聞 2010年10月27日付からの引用です。)
**************************************
『よく聞かれますけど、運命の一冊なんて、ないですよ。本に助けられたこともない。ただ、たくさんの本を読んでいるから、自分の身に降りかかったことが特別なこととは思いません。世の中にいくつもあることです。良いことも悪いことも、「全てあり得る」-本を読んだ人は、その当たり前のことが、わかるんじゃないでしょうか』
**************************************
文頭の内容と相反するように感じる方もいるかもしれませんが、俺は瀬戸内さんの考えもありだな・・・そう感じてます。
読んだ本のこの部分に共感した とか この章に心惹かれた・・・など本の一部の「いいとこ取り」もありだと思うのです。。。
さてさて、そんな読むだけで自分の内側でいろいろな事を思い描けるような経験が出来る読書ですが、本への想いや感想をアウトプットすることで、更に自分の中にに落とし込めることが出来る『読書会』を12月に長野市で開催します!!
日時、場所、課題本など詳細はこちらです。フォームからの申込か、このblogの『オーナーへメール』から申し込んでいただいてもオーケーです(*^_^*)
本を読んだ想いを話し聞くことで一冊の本の見方を深めてみませんか?
2010年10月24日
読書会 開催しました!!
さて先日、長野市において「第3回読書会」を開催しました。
課題本は「死ぬときに後悔すること25」

当日の模様はこちらのblogにアップしたので参照してくださいね^^
思いや気持ちをアウトプット(言葉に)することで、自分の中への落とし込みの度合いが格段と
違ってきます。
読書会に興味がある方 オーナー宛メール でお知らせ下さい。
次回読書会の詳細は こちら!!^^
課題本は「死ぬときに後悔すること25」

当日の模様はこちらのblogにアップしたので参照してくださいね^^
思いや気持ちをアウトプット(言葉に)することで、自分の中への落とし込みの度合いが格段と
違ってきます。
読書会に興味がある方 オーナー宛メール でお知らせ下さい。
次回読書会の詳細は こちら!!^^
2010年10月06日
読書会 参加者募集中
10月に入りやっと秋らしい日が訪れるようになりましたね。
さて来る10月20日に下記の要領で【読書会】開催いたします。
今回の課題本はエチカの鏡でも取り上げられ大反響があった
「死ぬときに後悔すること 25」
とします。
人は必ず「死」を迎えます。その時に人の心によぎるものは何か?どんな想いを残しているのか?
死を目前に迎えている患者を数多く見てきた終末期医療専門のドクターが書いたドキュメンタリーでもあります。
まだ少し参加人員に余裕があります。
自分を振り返る意味で、考えを話し(アウトプット)意見を聞く(インプット)時間を
意識して持つことが大切なことだと感じています。
そんな時間を持ちたい方の参加をお待ちしています。
********第二回 大人の学校 読書会について***********
●日時
2010年10月20日(水)19:00~21:00
●場所
コーチングアカデミーセミナールーム
380-0823 長野市南千歳1-3-7 アイビースクエア8F
※ターリーズコーヒーがあるビルの8Fです。
●参加費
500円(会場費)
課題図書はご自身でご購入下さい。
●募集人員
10人(最低開催人数:3名)
●課題本
大津秀一著「死ぬときに後悔すること25」
致知出版社
●読書会の目的
課題本を読んでの感想・意見をお互い発表し合うことで
本の内容について掘り下げ理解を深める。(事前に読んできて下さい。)
●話す内容について
今回の課題本では「死ぬときに後悔すること」として25項目が書かれています。
感想を話す場合、この中から2~3つを選んでいただき、その理由も一緒にお話をお願いします。
また死について書かれた本でお薦め本があればそれも発表して下さい。
(お薦め本がない場合は結構です。)
●お申込・お問い合わせ先
※氏名と電話番号を御連絡下さい。
コーチスクエア事務局「大人の学校」実行委員会
TEL 026-228-8676:受付時間12:00~19:00(平日のみ)
FAX 026-228-5801
email

****************************************
普段 本を読んでも一人で感じ、考えることが殆どだと思いますが、同じ本を読んだ人が
・「その本からどんなものを受け取ったのか?」
・「その本からどんな影響を受けたのか?」
・「こんな見方もあったのか!」
などその本に対する想いを話してみよう!!という趣旨です。
アウトプットすることで、本に対する理解は格段と向上します。
あまり堅苦しいものにせず、いろいろな見方や意見を聞いて経験してみよう!!という趣旨ですので
興味のある方は 上記連絡先 か オーナー宛メールで御連絡下さい<(_ _)>
皆様の御参加をお待ちしております。
さて来る10月20日に下記の要領で【読書会】開催いたします。
今回の課題本はエチカの鏡でも取り上げられ大反響があった
「死ぬときに後悔すること 25」
とします。
人は必ず「死」を迎えます。その時に人の心によぎるものは何か?どんな想いを残しているのか?
死を目前に迎えている患者を数多く見てきた終末期医療専門のドクターが書いたドキュメンタリーでもあります。
まだ少し参加人員に余裕があります。
自分を振り返る意味で、考えを話し(アウトプット)意見を聞く(インプット)時間を
意識して持つことが大切なことだと感じています。
そんな時間を持ちたい方の参加をお待ちしています。
********第二回 大人の学校 読書会について***********
●日時
2010年10月20日(水)19:00~21:00
●場所
コーチングアカデミーセミナールーム
380-0823 長野市南千歳1-3-7 アイビースクエア8F
※ターリーズコーヒーがあるビルの8Fです。
●参加費
500円(会場費)
課題図書はご自身でご購入下さい。
●募集人員
10人(最低開催人数:3名)
●課題本
大津秀一著「死ぬときに後悔すること25」
致知出版社
●読書会の目的
課題本を読んでの感想・意見をお互い発表し合うことで
本の内容について掘り下げ理解を深める。(事前に読んできて下さい。)
●話す内容について
今回の課題本では「死ぬときに後悔すること」として25項目が書かれています。
感想を話す場合、この中から2~3つを選んでいただき、その理由も一緒にお話をお願いします。
また死について書かれた本でお薦め本があればそれも発表して下さい。
(お薦め本がない場合は結構です。)
●お申込・お問い合わせ先
※氏名と電話番号を御連絡下さい。
コーチスクエア事務局「大人の学校」実行委員会
TEL 026-228-8676:受付時間12:00~19:00(平日のみ)
FAX 026-228-5801

****************************************
普段 本を読んでも一人で感じ、考えることが殆どだと思いますが、同じ本を読んだ人が
・「その本からどんなものを受け取ったのか?」
・「その本からどんな影響を受けたのか?」
・「こんな見方もあったのか!」
などその本に対する想いを話してみよう!!という趣旨です。
アウトプットすることで、本に対する理解は格段と向上します。
あまり堅苦しいものにせず、いろいろな見方や意見を聞いて経験してみよう!!という趣旨ですので
興味のある方は 上記連絡先 か オーナー宛メールで御連絡下さい<(_ _)>
皆様の御参加をお待ちしております。
タグ :読書会死ぬときに後悔すること
2010年09月17日
祖父たちの零戦
さて最近読んだ本を・・・
祖父たちの零戦
です。
これは戦時中 世界に名を馳せた「零戦~零式艦上戦闘機」に乗って戦った進藤三郎氏と鈴木實氏の両名を中心にした多くの戦闘機乗りの方々のドキュメントです。
子供の頃 撃墜王と呼ばれた坂井三郎氏の本を読んで、「カッコイイ」そう感じていた時もありました。
やはり子供だったので戦争の悲惨さより、戦闘機というメカニカルなもの、そしてそれを操縦するパイロットに
憧れがありました。
あとウオーターラインシリーズで戦艦や空母なんかもよく作ってました。
でも年齢を重ね戦争の実態を知るにつけ、憧れ だけでは済まされない部分を見るようになり興味が薄れてきました。がそんな気持ちとは逆に興味をもってきたのは「個人」としてあの戦争に関わった多くの人達の気持ちでした。
そんな中で今回 この本を読んだ訳ですが・・・
ドキュメンタリーですから、涙を抑えられないような物語(ちょっと前に読んだ「永遠の0」のような)とは違いますが
現実に起きていた出来事として、重く受け止めることが多くありました。
開戦当初の圧倒的強さから、徐々に敵に研究され櫛の歯が欠けるようにどんどん戦友達が亡くなっていく・・・
朝一緒に食事したのに、夕食の時にはもういない・・・。
戦争終盤にはアメリカ軍の逆襲のため撤退に次ぐ撤退をしていくなかで、負け犬のようにただ逃げるしかない状況の中から生み出された「新風特別攻撃隊」いわゆる 特攻 ですね・・・・。
以前は「負けると分かっていながら死に行くことは無駄だ・・」と思っていましたが、以前行った知覧の特攻会館での経験や上田の無言館での展示物を見たこと、そしてこの本を読んでみて、当時のあの状況、そしてそれまで主人公達が自分の人生として積み重ねた軍人としての経験や考え方、そして何より「自分の命でこの国を守りことが出来れば・・」
そんな切なる思いを持ったまま特攻で亡くなった人達を思う時、たった一言「無駄な死だった」とはとても言えないもの そう
今は断言出来ます。
多分 これからあの戦争を経験した人から生の声を聞く機会はどんどん減っていくと思います。
だからこそ、このような本を読み考えることは平和な時代に生まれきた我々の責務であるように思うのです。
祖父たちの零戦
です。
これは戦時中 世界に名を馳せた「零戦~零式艦上戦闘機」に乗って戦った進藤三郎氏と鈴木實氏の両名を中心にした多くの戦闘機乗りの方々のドキュメントです。
子供の頃 撃墜王と呼ばれた坂井三郎氏の本を読んで、「カッコイイ」そう感じていた時もありました。
やはり子供だったので戦争の悲惨さより、戦闘機というメカニカルなもの、そしてそれを操縦するパイロットに
憧れがありました。
あとウオーターラインシリーズで戦艦や空母なんかもよく作ってました。
でも年齢を重ね戦争の実態を知るにつけ、憧れ だけでは済まされない部分を見るようになり興味が薄れてきました。がそんな気持ちとは逆に興味をもってきたのは「個人」としてあの戦争に関わった多くの人達の気持ちでした。
そんな中で今回 この本を読んだ訳ですが・・・
ドキュメンタリーですから、涙を抑えられないような物語(ちょっと前に読んだ「永遠の0」のような)とは違いますが
現実に起きていた出来事として、重く受け止めることが多くありました。
開戦当初の圧倒的強さから、徐々に敵に研究され櫛の歯が欠けるようにどんどん戦友達が亡くなっていく・・・
朝一緒に食事したのに、夕食の時にはもういない・・・。
戦争終盤にはアメリカ軍の逆襲のため撤退に次ぐ撤退をしていくなかで、負け犬のようにただ逃げるしかない状況の中から生み出された「新風特別攻撃隊」いわゆる 特攻 ですね・・・・。
以前は「負けると分かっていながら死に行くことは無駄だ・・」と思っていましたが、以前行った知覧の特攻会館での経験や上田の無言館での展示物を見たこと、そしてこの本を読んでみて、当時のあの状況、そしてそれまで主人公達が自分の人生として積み重ねた軍人としての経験や考え方、そして何より「自分の命でこの国を守りことが出来れば・・」
そんな切なる思いを持ったまま特攻で亡くなった人達を思う時、たった一言「無駄な死だった」とはとても言えないもの そう
今は断言出来ます。
多分 これからあの戦争を経験した人から生の声を聞く機会はどんどん減っていくと思います。
だからこそ、このような本を読み考えることは平和な時代に生まれきた我々の責務であるように思うのです。
2010年09月01日
「優柔決断」のすすめ by 古田敦也氏
さて先日の日曜に行った 古田敦也氏講演会・・・
でその会場で購入したのがこの本 「優柔決断」のすすめ PHP新書 です^^;

講演会では、球界裏話的な話も多く、笑いに包まれて和やかな雰囲気でしたが、この本の内容も
結構話されていました。「優柔」とは普通ネガティブな印象を持ちますが、この本の中で古田さんはこんな表現をしていました。
「優柔とは読んで字の如く「優れた柔軟さ」と解釈してはみたらどうだろうか?」
現代のようにネット上でいろいろな情報が飛び交う世界では、そこから得られる情報量が膨大となりそれが返って頭でっかちとなり固定観念として植え付けられる様になってしまう・・・。
そうではなくもっと「柔軟に(柔らかく)」考え試行錯誤する気持ちが大切ではないか?と書かれています。
この文章を読んでコーチングで教えてもらったこんな言葉が重なりました。
「変化することを恐れない」
とかく人は(俺も含めて)以前の成功に囚われてしまい、なかなかやり方を変えようとしてもなかなか変えられないものです。
が、それは自分の成長を拒絶していることと同じ・・・。そこでいろいろなことを試してみることこそ成長の第一ステップだと書かれていて「あの言葉と同じじゃん!!」と本を読んでニンマリ しました。
しました。
更に古田さんは「優柔」することの重要性と同時に最後には 「決断」する=腹をくくる ことの大切さも強く書かれています。決断とは「決めて断つ」・・・何かを得るためには何かを捨てる必要性があると・・・そうだよな~結局捨てることを恐れるあまり、どちらも失うことってままあるし・・・^^;
その他にも魅力的な題目として本の中では
・現在の環境にグチを言わない
・ブレることを恐れない
・実際にやってみて自分のものにする
・成功イメージを描きすぎない
などこれからの生き方に生かしていけそうなたくさんの言葉と文章がありました。
さらには野村監督や若松監督、そして古田さん自身が経験した組織論なども書かれていて
元プロ野球選手が書いた本とは思えないくらい含蓄のある言葉が並んでいました。
(きっと古田さんなら会社などの組織の中でも部下の力を十二分に発揮して優秀なチームを作るんだろうな~)
スポーツの世界で一流と呼ばれた人の思考や感じ方が書かれた本がこんなにもおもしろいとは・・・
やはり古田さんはタダモノではない^^ そう感じさせてくれる一冊となりました。
でその会場で購入したのがこの本 「優柔決断」のすすめ PHP新書 です^^;

講演会では、球界裏話的な話も多く、笑いに包まれて和やかな雰囲気でしたが、この本の内容も
結構話されていました。「優柔」とは普通ネガティブな印象を持ちますが、この本の中で古田さんはこんな表現をしていました。
「優柔とは読んで字の如く「優れた柔軟さ」と解釈してはみたらどうだろうか?」
現代のようにネット上でいろいろな情報が飛び交う世界では、そこから得られる情報量が膨大となりそれが返って頭でっかちとなり固定観念として植え付けられる様になってしまう・・・。
そうではなくもっと「柔軟に(柔らかく)」考え試行錯誤する気持ちが大切ではないか?と書かれています。
この文章を読んでコーチングで教えてもらったこんな言葉が重なりました。
「変化することを恐れない」
とかく人は(俺も含めて)以前の成功に囚われてしまい、なかなかやり方を変えようとしてもなかなか変えられないものです。
が、それは自分の成長を拒絶していることと同じ・・・。そこでいろいろなことを試してみることこそ成長の第一ステップだと書かれていて「あの言葉と同じじゃん!!」と本を読んでニンマリ
 しました。
しました。更に古田さんは「優柔」することの重要性と同時に最後には 「決断」する=腹をくくる ことの大切さも強く書かれています。決断とは「決めて断つ」・・・何かを得るためには何かを捨てる必要性があると・・・そうだよな~結局捨てることを恐れるあまり、どちらも失うことってままあるし・・・^^;
その他にも魅力的な題目として本の中では
・現在の環境にグチを言わない
・ブレることを恐れない
・実際にやってみて自分のものにする
・成功イメージを描きすぎない
などこれからの生き方に生かしていけそうなたくさんの言葉と文章がありました。
さらには野村監督や若松監督、そして古田さん自身が経験した組織論なども書かれていて
元プロ野球選手が書いた本とは思えないくらい含蓄のある言葉が並んでいました。
(きっと古田さんなら会社などの組織の中でも部下の力を十二分に発揮して優秀なチームを作るんだろうな~)
スポーツの世界で一流と呼ばれた人の思考や感じ方が書かれた本がこんなにもおもしろいとは・・・
やはり古田さんはタダモノではない^^ そう感じさせてくれる一冊となりました。
2010年08月16日
永遠の0(ゼロ)
久々に頭を「ガツン!!」と叩かれ、胸の中に手を入れられてかきむし出されるような本でした。
昨日blogをアップした後、読み始めて、朝方には読み終えていた。。。それこそ「次は?この先は?」そんな
ことを感じながら時間を忘れて読みふけっていました。
(こんなのは「マークスの山」以来かも・・・・・。)
主人公は司法試験に4回落ちてこれからの人生をどう生きるかを見失い始めた26歳の青年です。
その彼の姉と一緒に戦闘機乗りの祖父の生き様を調べるところから物語は始まります。
それまで知らされていなかった祖父の生き様や考え方、なぜ祖父が「生き残る」事へこだわったのか。
その祖父と関わった人が「命」と「生きる」ことをそれぞれの立場で感じて考え、戦争を生き残り
その後の人生を生きてきたか が書かれていて、胸が締め付けられるようなそんな人達の想いを感じました。
この本の帯のこんな推薦文に書かれています。
「僕は号泣するのを懸命に歯を喰いしばってこらえた。が、ダメだった。」
まさにこの言葉が表すような本です。
俺のへたくそな文章で、この本に書かれている様な人達が当時感じていたことを
説明するのは止めたいと思います。
ともかく 読んで感じて欲しい そう思います。
追記
先の戦争は植民地支配を止めさせるため必要なものだった など戦争を美化する風潮が強くなっている様に感じます。
今の日本は戦争に向けて少しずつ歩みを進めているように感じてなりません。。。。
関連リンク
・神風~特攻エピソード~
・沖縄近海で特攻機の残骸見つかる 出撃記録と一致
・戦後65年 特攻を語る
昨日blogをアップした後、読み始めて、朝方には読み終えていた。。。それこそ「次は?この先は?」そんな
ことを感じながら時間を忘れて読みふけっていました。
(こんなのは「マークスの山」以来かも・・・・・。)
主人公は司法試験に4回落ちてこれからの人生をどう生きるかを見失い始めた26歳の青年です。
その彼の姉と一緒に戦闘機乗りの祖父の生き様を調べるところから物語は始まります。
それまで知らされていなかった祖父の生き様や考え方、なぜ祖父が「生き残る」事へこだわったのか。
その祖父と関わった人が「命」と「生きる」ことをそれぞれの立場で感じて考え、戦争を生き残り
その後の人生を生きてきたか が書かれていて、胸が締め付けられるようなそんな人達の想いを感じました。
この本の帯のこんな推薦文に書かれています。
「僕は号泣するのを懸命に歯を喰いしばってこらえた。が、ダメだった。」
まさにこの言葉が表すような本です。
俺のへたくそな文章で、この本に書かれている様な人達が当時感じていたことを
説明するのは止めたいと思います。
ともかく 読んで感じて欲しい そう思います。
追記
先の戦争は植民地支配を止めさせるため必要なものだった など戦争を美化する風潮が強くなっている様に感じます。
今の日本は戦争に向けて少しずつ歩みを進めているように感じてなりません。。。。
関連リンク
・神風~特攻エピソード~
・沖縄近海で特攻機の残骸見つかる 出撃記録と一致
・戦後65年 特攻を語る
2010年03月03日
読書会
さて先週の日曜(28日)に「サンデーヒルズ読書会」に参加してきました!!
参加者は10名というこぢんまりとした読書会でしたが、とてもいい刺激を受けてきました。
今回の課題本は上にもありますが中勘助「銀の匙」・・・
岩波文庫の部数ベスト10にも入る永きにわたるベストセラーです。
が,しかっし~!!
読み始めは・・・ほんと読みにくい・・というのが最初の感想でした。
他の方も同じような意見が多かった・・・(笑)
主人公が子供ということもありますが、物語として起伏が少なく、間延びした(失礼<(_ _)>)ような印象を最初は持ちました・・。
情景や表現がとても繊細で瑞々しいのですが逆に、主人公の個性(というのかな)があまり文中で感じることが出来なかったのが一番大きな理由かも・・・^^;
でも、読み進めていくうちにあるところから、この本にのめり込む自分がいました。
そのきっかけは・・主人公が女の子と出会い淡い恋心をいだく場面あたりからです。
その女の子と出会ったことで主人公が急速に、成長していく頃には主人公の叔父になったような気持ちでした(笑)
参加された方々はいろいろな職業、年齢もまちまちでしたが、自分一人の見方だけではなく他の方の感想や
印象など聞いて再度 この作品を読み直してみたい そんな気持ちを持ちました・・。
やっぱりインプットだけではなく、アウトプットすることで一段と読みが深くなり刺激を受けますね~。
次回は「雪」・・・・
少しずつ読んでますが、どんな印象をもつか楽しみです(*^_^*)
2010年02月23日
喜多川泰さん 新作です!!
さて TOPにも掲載していますが、3月6日 講演会をお願いしている
喜多川泰さんの新作が2月25日に幻冬舎から出版されます。
※早速Amazonに予約済み
どんな内容なのか、今からとても楽しみです。
喜多川泰さんの新作が2月25日に幻冬舎から出版されます。
※早速Amazonに予約済み

どんな内容なのか、今からとても楽しみです。
2010年02月22日
こんな方法で検索があった!!^^
2010年02月03日
ないもの、あります
というふざけた(笑)題名に惹かれて買ってしまいました・・・^^;

更に単行本のくせに価格が¥900もしやがるし~~
(思わずレジで金額を聞いて(* ̄0 ̄)/ オゥッ!! 普通の単行本の2倍近い・・・)
で、だまされた(笑)と思って読んでみると・・・おもしろい・・・・(^^;ゞポリポリ
ないもの、あります を謳い文句に売り出している商品の一例は・・・
・堪忍袋の緒
・無鉄砲
・他人のふんどし
etcetc・・・
まー 確かに収録されたものは普通(笑)の店ではないよな~
でもこの本に取り上げられたものって、読んでいくうちに「実際ありそう~」と思わせる文章の巧みさがあって読みながら笑ってしまった^^;
例えば「堪忍袋の緒」の説明
「ケンカっ早い方のために「江戸っ子仕様」の「鋼鉄製」も御用意いたしております。」という非常にうま~~い^^説明があり思わず「欲しい!!」と言ってしまいそうになりました^^;
「無鉄砲」では
「なお、本物の<鉄砲>と<無鉄砲>とを同時に所有することは、子供であれ、大人であれ、法律で固く禁じられています。くれぐれも御注意ください。」なんて本の中の虚実が綯い交ぜに書かれていたり・・・。
非常に含蓄のある(本当か?!(笑))楽しい本でしたよ。
もし本屋さんで見かけたら、手にとって見て下さいね。
この本は ないもの ではありませんから・・・・(笑)

更に単行本のくせに価格が¥900もしやがるし~~
(思わずレジで金額を聞いて(* ̄0 ̄)/ オゥッ!! 普通の単行本の2倍近い・・・)
で、だまされた(笑)と思って読んでみると・・・おもしろい・・・・(^^;ゞポリポリ
ないもの、あります を謳い文句に売り出している商品の一例は・・・
・堪忍袋の緒
・無鉄砲
・他人のふんどし
etcetc・・・
まー 確かに収録されたものは普通(笑)の店ではないよな~
でもこの本に取り上げられたものって、読んでいくうちに「実際ありそう~」と思わせる文章の巧みさがあって読みながら笑ってしまった^^;
例えば「堪忍袋の緒」の説明
「ケンカっ早い方のために「江戸っ子仕様」の「鋼鉄製」も御用意いたしております。」という非常にうま~~い^^説明があり思わず「欲しい!!」と言ってしまいそうになりました^^;
「無鉄砲」では
「なお、本物の<鉄砲>と<無鉄砲>とを同時に所有することは、子供であれ、大人であれ、法律で固く禁じられています。くれぐれも御注意ください。」なんて本の中の虚実が綯い交ぜに書かれていたり・・・。
非常に含蓄のある(本当か?!(笑))楽しい本でしたよ。
もし本屋さんで見かけたら、手にとって見て下さいね。
この本は ないもの ではありませんから・・・・(笑)
2010年01月09日
葉祥明
年末に市立図書館に行ったら懐かしい絵に再会しました。

北海道の中学・高校時代、おふくろが毎月購読していた雑誌に「詩とメルヘン」という本がありました。
当時はおふくろより俺の方がよく読んでいたかもしれません。
編集長は やなせたかしさん
当時 掲載されていた作家やイラストレータさんは
・東君平さん
・おおた慶文さん
・黒井健さん
・林静一さん
などたくさんの方々が挿絵を描いていました。
その中の一人に 今回図書館で再会した 葉祥明さん がいました。
地平線の絵が強く印象に残っていたのですが、今回図書館で見た本の内容は、絵から受ける印象とは正反対のような文章が綴られていました。
その文章を読んだ時、雑誌で見ていた印象のある絵を描いていた「葉祥明」さんではなく
生き方や仕事、生活のために絵を描かざるを得ない状況などが正直に書かれてました。が・・・
今の俺にとっては逆に新鮮な印象を受けました・・・。
そんな文と絵に惹かれて買ってしましたよ。葉祥明さんの本・・・それも2冊(笑)
写真は「地平線の彼方」と「僕と風の対話」・・・
やっぱり「風を感じて」と題した者としては「風」は外せません(笑)

北海道の中学・高校時代、おふくろが毎月購読していた雑誌に「詩とメルヘン」という本がありました。
当時はおふくろより俺の方がよく読んでいたかもしれません。
編集長は やなせたかしさん
当時 掲載されていた作家やイラストレータさんは
・東君平さん
・おおた慶文さん
・黒井健さん
・林静一さん
などたくさんの方々が挿絵を描いていました。
その中の一人に 今回図書館で再会した 葉祥明さん がいました。
地平線の絵が強く印象に残っていたのですが、今回図書館で見た本の内容は、絵から受ける印象とは正反対のような文章が綴られていました。
その文章を読んだ時、雑誌で見ていた印象のある絵を描いていた「葉祥明」さんではなく
生き方や仕事、生活のために絵を描かざるを得ない状況などが正直に書かれてました。が・・・
今の俺にとっては逆に新鮮な印象を受けました・・・。
そんな文と絵に惹かれて買ってしましたよ。葉祥明さんの本・・・それも2冊(笑)
写真は「地平線の彼方」と「僕と風の対話」・・・
やっぱり「風を感じて」と題した者としては「風」は外せません(笑)
2009年12月20日
イーグルに訊け~インディアンに学ぶ人生哲学~
さて今 天外伺朗さん、衛藤信之さん共著 「イーグルに訊け」を読んでいます。

元々 衛藤さんの「心時代の夜明け」を見て手を出してみました(笑)
天外さんはこの本を読むまで知らなかったのですが、SONY在籍中には ワークステーションのNEWSやAIBOの開発を主導された方だと初めて知りました・・。(NEWS・・・なつかしい名前ですね~^^;)
さて内容は・・・
・インディアンの世界観
・感じることの大切さ
・奇跡は自分の中にある
などです。
まだ読中ですがじっくり読み進めていきますね^^ 続きを読む

元々 衛藤さんの「心時代の夜明け」を見て手を出してみました(笑)
天外さんはこの本を読むまで知らなかったのですが、SONY在籍中には ワークステーションのNEWSやAIBOの開発を主導された方だと初めて知りました・・。(NEWS・・・なつかしい名前ですね~^^;)
さて内容は・・・
・インディアンの世界観
・感じることの大切さ
・奇跡は自分の中にある
などです。
まだ読中ですがじっくり読み進めていきますね^^ 続きを読む
2009年11月18日
ジーパンをはく中年は幸せになれない
ってとっても刺激的な題名だと思いませんか?(笑)
最初にこの本の題名を読んだ時、思わず「なにお~~!!!」と思いました。(笑)
(はい そこの同世代の方(笑)そう思いませんか?^^;)
でその本の写真です。

そんな気持ちにさせておいて帯には「ムッとしないでまず読んでほしい」・・・・
これ うまい惹きだな~と思いながら術中に嵌り手にとってみました。(笑)
で本屋でざっと目を通したら・・・・これがおもしろい、おもしろい(笑)
内容は人の心理におけるいろいろな矛盾や疑問点をおもしろおかしく、わかりやすく書かれていて帰りの電車内で夢中になって読みました←ブックカバーありで``r(^^;)ポリポリ
例えば題名である「ジーパンをはく中年は幸せになれない」については、中年のジーパンの心理を考えると題して分析を加えていますが、妙に納得(苦笑)出来るところが多い・・・^^;以前は
子供の服装(小学生の半ズボン)→若者の服装(ジーンズ)→大人の服装(年齢にふさわしい服装)
という流れがあったのに、今は若者から大人への服装の転換の境目がなくなっている。
また今では大人で若い服装が似合うことがある種ステータスになっている・・。
では今の大人(中年)の体型や皮膚は以前と違うの?お腹がでたり、二重あごになっていないの?・・・o(´^`)o ウー耳が痛いぞ
若さを保っているのは肉体以上に精神の方・・気が若いからファッション、振る舞い、見た目も若い。世の中はそれが許されているし、それで幸福(定義は人それぞれでしょうが)な戦争のない世の中となっている。
でも著者は「それでいいの?甘いものを食べ予防しないで虫歯になるように、後でしっぺ返しはありませんか?」と読者に問いかけています。
そしてそこから
・自分の年齢になじめない
・「中年になると治るはず」の心の病が治らない
・思春期の危機
など興味深い内容で話を進めていきます。
ジーンズの件では
「ファッションとしてジーパンを選択しているだけならいいが、それが心の衣替えを拒否していることの表れの場合、歳をとること自体が不幸として心にのしかかってくる」
そんな風に書いていて,自分の中ではとても腑に落ちた気がしました^^;
他にも
・大切な仕事の前日ほど深酒したくなる
・いちばん好きなものを、なぜか選べない
・みんなで考えると間違える
などなど読んでいて「ほー」とか「へー」とか関心するようなことがたくさん書かれていました。
そして最後の章ではこんなことが書かれていました。
「何歳になっても、人は何かを生み出せる」
この言葉は心に焼き付けておきたいと思っています^^;
追記
「ジーパン」という呼び方自体、何か懐かしい(太陽にほえろ!)匂いを感じるのは俺だけでしょうか?(^^ゞ
こんな記事もありました~(笑)
最初にこの本の題名を読んだ時、思わず「なにお~~!!!」と思いました。(笑)
(はい そこの同世代の方(笑)そう思いませんか?^^;)
でその本の写真です。

そんな気持ちにさせておいて帯には「ムッとしないでまず読んでほしい」・・・・
これ うまい惹きだな~と思いながら術中に嵌り手にとってみました。(笑)
で本屋でざっと目を通したら・・・・これがおもしろい、おもしろい(笑)
内容は人の心理におけるいろいろな矛盾や疑問点をおもしろおかしく、わかりやすく書かれていて帰りの電車内で夢中になって読みました←ブックカバーありで``r(^^;)ポリポリ
例えば題名である「ジーパンをはく中年は幸せになれない」については、中年のジーパンの心理を考えると題して分析を加えていますが、妙に納得(苦笑)出来るところが多い・・・^^;以前は
子供の服装(小学生の半ズボン)→若者の服装(ジーンズ)→大人の服装(年齢にふさわしい服装)
という流れがあったのに、今は若者から大人への服装の転換の境目がなくなっている。
また今では大人で若い服装が似合うことがある種ステータスになっている・・。
では今の大人(中年)の体型や皮膚は以前と違うの?お腹がでたり、二重あごになっていないの?・・・o(´^`)o ウー耳が痛いぞ
若さを保っているのは肉体以上に精神の方・・気が若いからファッション、振る舞い、見た目も若い。世の中はそれが許されているし、それで幸福(定義は人それぞれでしょうが)な戦争のない世の中となっている。
でも著者は「それでいいの?甘いものを食べ予防しないで虫歯になるように、後でしっぺ返しはありませんか?」と読者に問いかけています。
そしてそこから
・自分の年齢になじめない
・「中年になると治るはず」の心の病が治らない
・思春期の危機
など興味深い内容で話を進めていきます。
ジーンズの件では
「ファッションとしてジーパンを選択しているだけならいいが、それが心の衣替えを拒否していることの表れの場合、歳をとること自体が不幸として心にのしかかってくる」
そんな風に書いていて,自分の中ではとても腑に落ちた気がしました^^;
他にも
・大切な仕事の前日ほど深酒したくなる
・いちばん好きなものを、なぜか選べない
・みんなで考えると間違える
などなど読んでいて「ほー」とか「へー」とか関心するようなことがたくさん書かれていました。
そして最後の章ではこんなことが書かれていました。
「何歳になっても、人は何かを生み出せる」
この言葉は心に焼き付けておきたいと思っています^^;
追記
「ジーパン」という呼び方自体、何か懐かしい(太陽にほえろ!)匂いを感じるのは俺だけでしょうか?(^^ゞ
こんな記事もありました~(笑)
2009年11月06日
閑話休題
今日もいい天気ですね~
ここしばらく真面目で固い(笑)本ばっかり読んでいたので、ちょっと嗜好を変えてこんな本を読んでみました。
「日本人の知らない日本語」

これって日本語学校の先生である海野凪子さんが実際に経験したことに基づいて書かれているんだけど・・・もう読んだとたん爆笑もんでした。あははは^^;
例えばこんな例・・・・
(先生)「たっていってみてください」
(生徒)「た」・・・・・
先生は「(立って)いってみてください」と言ったのに生徒さんは「(た)っていってみてください」と
理解している・・・・・(笑)
その他にも日本語独特の「助数詞」の話とか・・・(例えば大きな動物は「頭」だけど小動物は「匹」とか)これも改めて問題として出されると難しいです。ハイ(*゜.゜)ゞ・・・昆布の数え方なんかわかりますか?^^;
来日された方にとって日本語って本当に難しいですよね。ネイティブ・ジャパニーズである我々でも改めて考えると「難しいよな~日本語」って感じます^^;
日本人同士だからって、意思が確実に伝わっているか?となると難しいでしょうね。だからこそコミュニケーション講座とか話し方、聴き方講座とかが流行るんだと思います。
コーチングでも、受取る人の心の状態や理解力の違いをきちんと確認しないと、とんでもない間違いしちゃうだろうな・・・この本読んでそう感じました。←なんだ 結局真面目な見解になるのね・・・・ (笑)
(笑)
ここしばらく真面目で固い(笑)本ばっかり読んでいたので、ちょっと嗜好を変えてこんな本を読んでみました。
「日本人の知らない日本語」

これって日本語学校の先生である海野凪子さんが実際に経験したことに基づいて書かれているんだけど・・・もう読んだとたん爆笑もんでした。あははは^^;
例えばこんな例・・・・
(先生)「たっていってみてください」
(生徒)「た」・・・・・
先生は「(立って)いってみてください」と言ったのに生徒さんは「(た)っていってみてください」と
理解している・・・・・(笑)
その他にも日本語独特の「助数詞」の話とか・・・(例えば大きな動物は「頭」だけど小動物は「匹」とか)これも改めて問題として出されると難しいです。ハイ(*゜.゜)ゞ・・・昆布の数え方なんかわかりますか?^^;
来日された方にとって日本語って本当に難しいですよね。ネイティブ・ジャパニーズである我々でも改めて考えると「難しいよな~日本語」って感じます^^;
日本人同士だからって、意思が確実に伝わっているか?となると難しいでしょうね。だからこそコミュニケーション講座とか話し方、聴き方講座とかが流行るんだと思います。
コーチングでも、受取る人の心の状態や理解力の違いをきちんと確認しないと、とんでもない間違いしちゃうだろうな・・・この本読んでそう感じました。←なんだ 結局真面目な見解になるのね・・・・
 (笑)
(笑) 2009年11月05日
たぁくらたぁ
という雑誌を購入しました^^;発行元は 上松にある「オフィスM」さん・・・
今回は市長選の前に発行されていた号でしたが・・・・

なんか読めば読むほど・・・・今回の市長選 また考えちまう・・・ほんとにいいの?って?
市民会館のこと、産業廃棄物行政のこと、トイーゴとその後の管理運用費が約5千万/年かかっていること・・・なんか考えると「どよーん 」となりますが・・。
」となりますが・・。
さて時間があるので現在濫読中・・・(笑)
最近読んだのはこれ 神様のカルテ

たまたま週末の上京の際に新幹線で読んだのですが・・・・・
途中 読むのを止めました(笑) だってやばいんだもん^^;
長野(松本)が舞台ということもありますが、登場人物がみな優しい・・・
主人公を支える看護師さんがいいな そう感じました。みんな素直に(心を)出せないけど
裏ではしっかり支えているとこなんて・・・うん。(笑)←趣味入ってないか~という突っ込みはなしでね^^
さて今「ジーパンをはく中年は幸せになれない」という本を読んでいます。
心理学の本なんですが結構おもしろい・・・・たまたま駅ナカの本屋で買ったのですが(^^)bGood! (OK!)
さてのんびり読むか・・・(笑)
今回は市長選の前に発行されていた号でしたが・・・・

なんか読めば読むほど・・・・今回の市長選 また考えちまう・・・ほんとにいいの?って?
市民会館のこと、産業廃棄物行政のこと、トイーゴとその後の管理運用費が約5千万/年かかっていること・・・なんか考えると「どよーん
 」となりますが・・。
」となりますが・・。さて時間があるので現在濫読中・・・(笑)
最近読んだのはこれ 神様のカルテ

たまたま週末の上京の際に新幹線で読んだのですが・・・・・
途中 読むのを止めました(笑) だってやばいんだもん^^;
長野(松本)が舞台ということもありますが、登場人物がみな優しい・・・
主人公を支える看護師さんがいいな そう感じました。みんな素直に(心を)出せないけど
裏ではしっかり支えているとこなんて・・・うん。(笑)←趣味入ってないか~という突っ込みはなしでね^^
さて今「ジーパンをはく中年は幸せになれない」という本を読んでいます。
心理学の本なんですが結構おもしろい・・・・たまたま駅ナカの本屋で買ったのですが(^^)bGood! (OK!)
さてのんびり読むか・・・(笑)
2009年09月24日
白洲正子 その後
さて以前 白洲正子さんの本を図書館から借りたということをblogにアップしました。で読み始めて中間あたりを過ぎてますが図書館へ返すのがもったいない(笑)ので思わずAmazonで買ってしまいました。

読んでいて感じたのは「白洲正子さんは本物だ。自分で体験して考え痛い目にもあってその中で自分で言葉を選んで素直に正直に書いている人」今はそんな印象を持っています。
これまでは白洲次郎さんの書籍を読んできましたが、本人が著作のものは知っている限りこれしかありません。それに比べて正子さんの本が多いこと多いこと・・・(笑)
(でAmazonからこんなメールが・・・・商売うまいぞ!!Amazon(笑))
さてさてまた少し読んで気にいった言葉を書き留めてみたいと思いますね^^ 続きを読む

読んでいて感じたのは「白洲正子さんは本物だ。自分で体験して考え痛い目にもあってその中で自分で言葉を選んで素直に正直に書いている人」今はそんな印象を持っています。
これまでは白洲次郎さんの書籍を読んできましたが、本人が著作のものは知っている限りこれしかありません。それに比べて正子さんの本が多いこと多いこと・・・(笑)
(でAmazonからこんなメールが・・・・商売うまいぞ!!Amazon(笑))
さてさてまた少し読んで気にいった言葉を書き留めてみたいと思いますね^^ 続きを読む
2009年09月21日
白洲正子
2日続けていい天気ですね~~^^
こんな日はバイクで・・・という気持ちがとっても(いや思いっきり(笑))募るのですが
いかんせん まだピンが頭にあるので無理が出来ません
昨日は義父の納骨で梓川まで・・・
高速を使ったのですが、多くのライダーを見かけました。
そんな多くのライダーを見て「あー 俺もあんな風に見られているんのかな?」と思いました。
余裕で走っているライダー、なんか必死に針路変更を繰り返して抜いていくライダー、仲間とつるみながら楽しそうに走っているライダー・・・
やっぱり見ていて カッコイイ ライダーでありたいと思いました。(笑)
さてそんな連休なのですが、まだちょっと無理は出来ないので図書館で本を借りて読んでいます。
その借りた本の中で今回 白洲正子さん のエッセイがあります。
題は「美しくなるにつれて若くなる」
白洲次郎さんの奥さんでもあり、陶芸、能やエッセイなど幅広く活躍された女性です。
元々(笑)白洲次郎さんに興味を持ち、関連本など読んでいたのですが、これまでは白洲正子さんの本は一度も読んでいませんでした。今まだ読み始めたばかりですが、沢山の素敵な、含蓄のある言葉がたくさんあります。
・「人間」に年などありません。若くとも一所(ひとつところ)にじっとしているならば、それは既に老いたのです。
・他人は鏡です。
・恋は盲目といいますが、相手の色々なことが見えるようでは、ほんとにほれてはいない証拠です。案外盲人こそが、私達の解からないことが見えているのかも知れません。
等々・・・
まだこれから読み進めていきますが、たくさんいい言葉を教えてもらえそうな気がしています。
こんな日はバイクで・・・という気持ちがとっても(いや思いっきり(笑))募るのですが
いかんせん まだピンが頭にあるので無理が出来ません

昨日は義父の納骨で梓川まで・・・
高速を使ったのですが、多くのライダーを見かけました。
そんな多くのライダーを見て「あー 俺もあんな風に見られているんのかな?」と思いました。
余裕で走っているライダー、なんか必死に針路変更を繰り返して抜いていくライダー、仲間とつるみながら楽しそうに走っているライダー・・・
やっぱり見ていて カッコイイ ライダーでありたいと思いました。(笑)
さてそんな連休なのですが、まだちょっと無理は出来ないので図書館で本を借りて読んでいます。
その借りた本の中で今回 白洲正子さん のエッセイがあります。
題は「美しくなるにつれて若くなる」
白洲次郎さんの奥さんでもあり、陶芸、能やエッセイなど幅広く活躍された女性です。
元々(笑)白洲次郎さんに興味を持ち、関連本など読んでいたのですが、これまでは白洲正子さんの本は一度も読んでいませんでした。今まだ読み始めたばかりですが、沢山の素敵な、含蓄のある言葉がたくさんあります。
・「人間」に年などありません。若くとも一所(ひとつところ)にじっとしているならば、それは既に老いたのです。
・他人は鏡です。
・恋は盲目といいますが、相手の色々なことが見えるようでは、ほんとにほれてはいない証拠です。案外盲人こそが、私達の解からないことが見えているのかも知れません。
等々・・・
まだこれから読み進めていきますが、たくさんいい言葉を教えてもらえそうな気がしています。
2009年08月16日
気骨の判決
NHKの「気骨の判決」を見ましたか?題名と同じ骨太の作品でしたね。
戦争真っ只中 周り全てが戦争への嵐に巻き込まれる中ただ一人(いや正確には賛同者もいたのですが)自分の信念に基づいて戦争へ賛同した違法な選挙結果に対しを明確に「選挙無効」の判断した気骨のある大審院判事吉田久を描いています。
正直・・・物語的(脚本的)にはもう少し厚み(奥深さ)があれば・・・そんな風に感じましたが伝えたかった趣旨は十分伝わりました。
当時の世論や風潮全てが戦争翼賛に進む中、戦争を突き進めようとする組織や個人からいろいろな葛藤、脅迫、上司や大臣からの圧力等々・・・。
戦争に反対するためではなく、なにが真実なのか。そのことを法に照らし合わせて厳格にそして冷静に判決した吉田久判事は仕事に対する厳しさ、周りに対する配慮など尊敬できるものだと思います。
体制や世の中の流れ、また個人的な感情にも振られながらもがき苦しみながらも法律家としての矜持に従った判決を、当時の世の中で下した吉田判事のすごさに感動しました。
もしこれが今の世の中で、また、同じような流れの中になったとき
法律に携わる人達がどんな判断をくだすでしょうか?
そして飯塚事件のように冤罪の可能性がある人に死刑判決だす人達(最高裁判事)が本当に最高裁判事としての資格があるのか?
今度の選挙で判決例など見て考えたいと思います。
戦争真っ只中 周り全てが戦争への嵐に巻き込まれる中ただ一人(いや正確には賛同者もいたのですが)自分の信念に基づいて戦争へ賛同した違法な選挙結果に対しを明確に「選挙無効」の判断した気骨のある大審院判事吉田久を描いています。
正直・・・物語的(脚本的)にはもう少し厚み(奥深さ)があれば・・・そんな風に感じましたが伝えたかった趣旨は十分伝わりました。
当時の世論や風潮全てが戦争翼賛に進む中、戦争を突き進めようとする組織や個人からいろいろな葛藤、脅迫、上司や大臣からの圧力等々・・・。
戦争に反対するためではなく、なにが真実なのか。そのことを法に照らし合わせて厳格にそして冷静に判決した吉田久判事は仕事に対する厳しさ、周りに対する配慮など尊敬できるものだと思います。
体制や世の中の流れ、また個人的な感情にも振られながらもがき苦しみながらも法律家としての矜持に従った判決を、当時の世の中で下した吉田判事のすごさに感動しました。
もしこれが今の世の中で、また、同じような流れの中になったとき
法律に携わる人達がどんな判断をくだすでしょうか?
そして飯塚事件のように冤罪の可能性がある人に死刑判決だす人達(最高裁判事)が本当に最高裁判事としての資格があるのか?
今度の選挙で判決例など見て考えたいと思います。